
どうも!
週3回筋トレしているフツメンです!
トレーニーの皆さん、いつも筋トレお疲れ様です♪
きっとこの記事の読者さんは、普段からジムで筋トレする習慣を持ち、ある程度身体も仕上がっている人だと思います。
しかし、「ここ最近重量が伸びない…」「頑張っている割には成果が出なくなってきた…」と悩んでいるのではないでしょうか?



だからこの記事を開いてくれたんですよね?
もしかしたらそれは “プラトー” に陥っているかもしれません。
プラトーとは努力しても成長が停滞してしまう停滞期のことで、筋トレを続けていれば誰にでも起こりうることです。
しかし、これを知らないがゆえに「これ以上やっても無駄だ…」と感じ、ジムをやめてしまう人が一定数存在します。



これは非常にもったいない!!
そうならない為にも、プラトーになりやすい人の特徴とその解決策についてしっかり学んでおきましょう!
そこで、今回は筋トレが停滞する人の3つの特徴と今すぐ変えるべき効果的な対策5選をお伝えしたいと思います。
・プラトーになりやすい人の特徴が分かる
・プラトーを抜け出すきっかけになる
・効果的な解決方法が分かる
それではいきましょう!
筋トレが停滞する人の3つの特徴


新鮮な刺激を与えられていない
まず、多くの人が「筋トレをすれば筋肉が付く」ということは何となく知っているかと思います。
しかし、「なぜ筋トレをすると筋肉が付くの?」と聞かれたら言葉に詰まるのではないでしょうか?
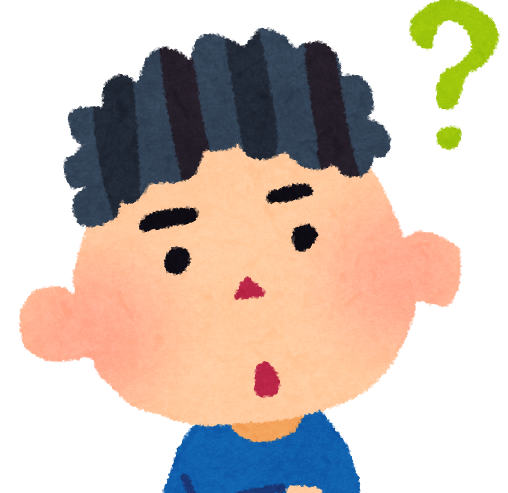
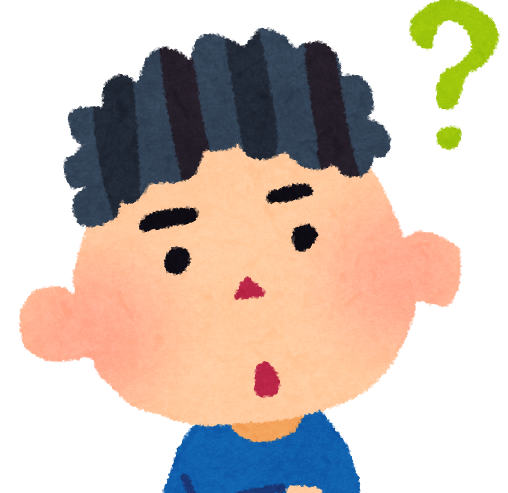
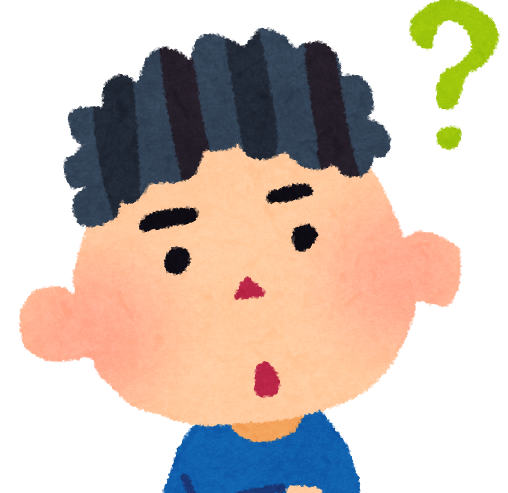
確かによく分からん…
実は、筋肉というのは「ストレスへの応答反応」によって大きく成長しようとするのです。
これはどういうことかと言いますと、筋トレのように強い負荷がかかる刺激というのは身体からするとかなりのストレスです。
仮に今の自分の力を100とした時、1~100の刺激では今の筋肉量のままでも耐えられることになりますので、筋肉は成長しようとしません。
しかし、101以上の刺激が加わると限界を超えてしまいますので、「次に同じようなストレスが来ても耐えられるように大きくなろう」と脳へシグナルが送られます。



このシグナルを受けて筋肉は大きく成長するのです!
つまり、筋トレでは今の限界をほんの少しだけ超えるような刺激が大切となります。



これが筋合成のスイッチ!
しかし、筋トレを習慣化している多くの人が毎回同じ順番で同じ種目、同じ重量で同じ回数のトレーニングをしてしまいがちです。
これでは筋肉からすると「はいはい、今日もまたいつものルーティーンね!(笑)」としか感じません。
たとえ自分では追い込んでいるつもりでも筋肉からすると、わざわざ筋合成するほどの刺激ではないのです。
そこで、重要なのが筋肉に毎回新鮮な刺激を与えてあげることです。



具体的な方法については後述します♪
「頑張れば頑張るほど成果が出る」という思い込みがある
先ほど「筋トレでは限界をほんの少しだけ超えるような刺激が大切」とお伝えしました。
しかし、僕たち日本人は真面目で根性もあって努力家の人が多い為、よくここを勘違いしてしまいます。
特に学生時代に部活動やサークルに励んでいた人や仕事を必死に頑張ってきた人ほどハマってしまうのが、「頑張れば頑張るほど成果が出る」という思考の罠。
もちろん、筋トレにおいてもやればやるほど「トレーニングの技術面」に関しては上手くなりますが、だからと言って筋肉が成長する訳ではありません。
あくまで「必要なのは限界を “ほんの少しだけ” 超えるような刺激」です。
もし「毎日2~3時間も筋トレして誰よりも努力しているのに伸びない…」と感じているのなら、あなたもその罠にハマっているかもしれません。
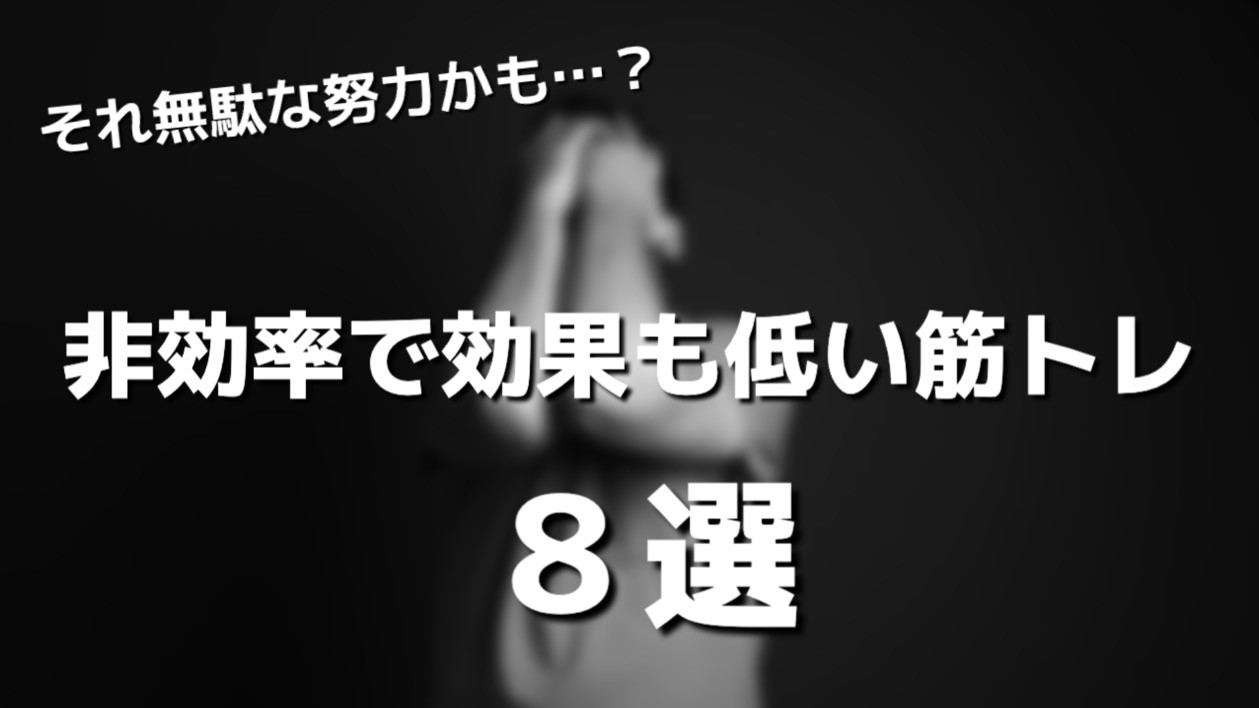
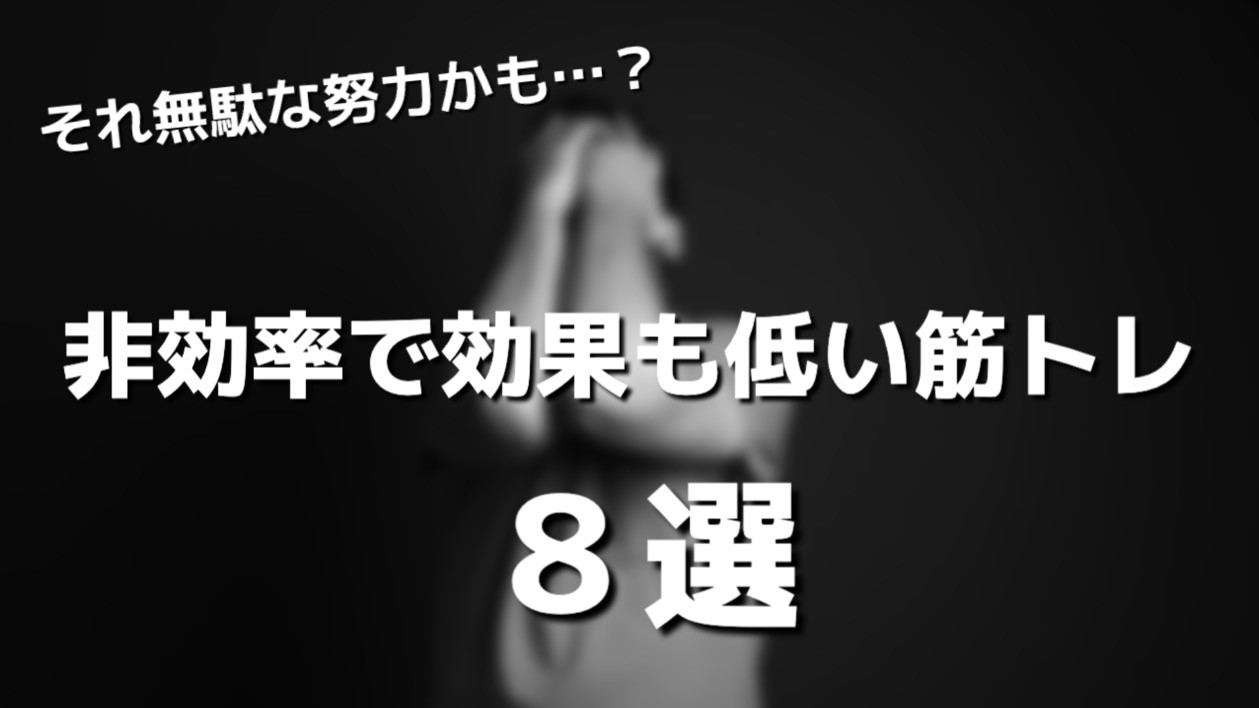
トレーニングの頻度が低すぎる
筋トレには大きく分けて「全身法」と「分割法」の2つのやり方があります。
それぞれのやり方については、以下のようになります。
全身法…1回で全身を鍛える方法
分割法…全身を何部位かに分けて、日ごとに違う部位を鍛える方法
例えば、(月)(木)(土)で週に3回筋トレをする場合
全身法では3日間とも「胸、背中、肩、腕、脚、腹」を鍛えます。
これに対し、分割法では「月曜…胸と背中」「木曜…肩と腕」「土曜…脚と腹」といった感じです。
トレーニングに慣れてくると、筋肉も大きくなり、扱う重量も重くなるので、1回に全身を追い込む全身法はかなり大変になってきます。
そこで、多くの人が分割法を取り入れる訳ですが、中には1回に1部位で分割のサイクルを組む人もいます。
この場合、週のスケジュールが以下のような感じになります。
月曜…胸 火曜…背中 水曜…休み
木曜…肩 金曜…腕 土曜…脚 日曜…休み
※腹だけの日を作る人は少ないので割愛します
これはあくまで一例ですが、1日1部位の分割ですと、休みも入れると各部位を週に1回しか刺激することが出来ません。
1週間で1周してキリが良いのですが、筋肉を大きくしたい場合、これでは少し頻度が低すぎるのです。
\ 筆者おすすめのホエイプロテイン /
筋トレが停滞したら変えるべき効果的な対策5選


ここからはプラトーに陥った際の効果的な対策について順番に見ていきましょう!
種目や順番を変える
先ほどプラトーになりやすい人は「毎回同じ順番で同じ種目のトレーニングをしてしまいがち」とお伝えしました。
ということは、逆に言えば種目や順番を変えてしまえばいいだけなのです。
例えば、「胸トレ」をいつも以下のような流れで行なっているとします。
1種目目:ベンチプレス
2種目目:インクラインダンベルフライ
3種目目:ケーブルクロス
この場合、以下のように種目を変えてしまえばいいのです。
1種目目:インクラインベンチプレス
2種目目:フラットのダンベルフライ
3種目目:ディップス
もちろん、1種目変えるだけでも違う刺激になりますし、今回の例のように思い切って3種目とも変えてしまってもOKです。
また、種目を変えたくないという人は順番を変えてみるのはいかがでしょうか?
種目は変わらなくても順番が入れ替わるだけで筋肉は違う刺激として受け取りますので、おすすめのやり方です。
1種目目:インクラインダンベルフライ
2種目目:ベンチプレス
3種目目:ケーブルクロス
これくらいの変化なら誰でも出来るのではないでしょうか?



ぜひ伸び悩んだ時はお試しください♪
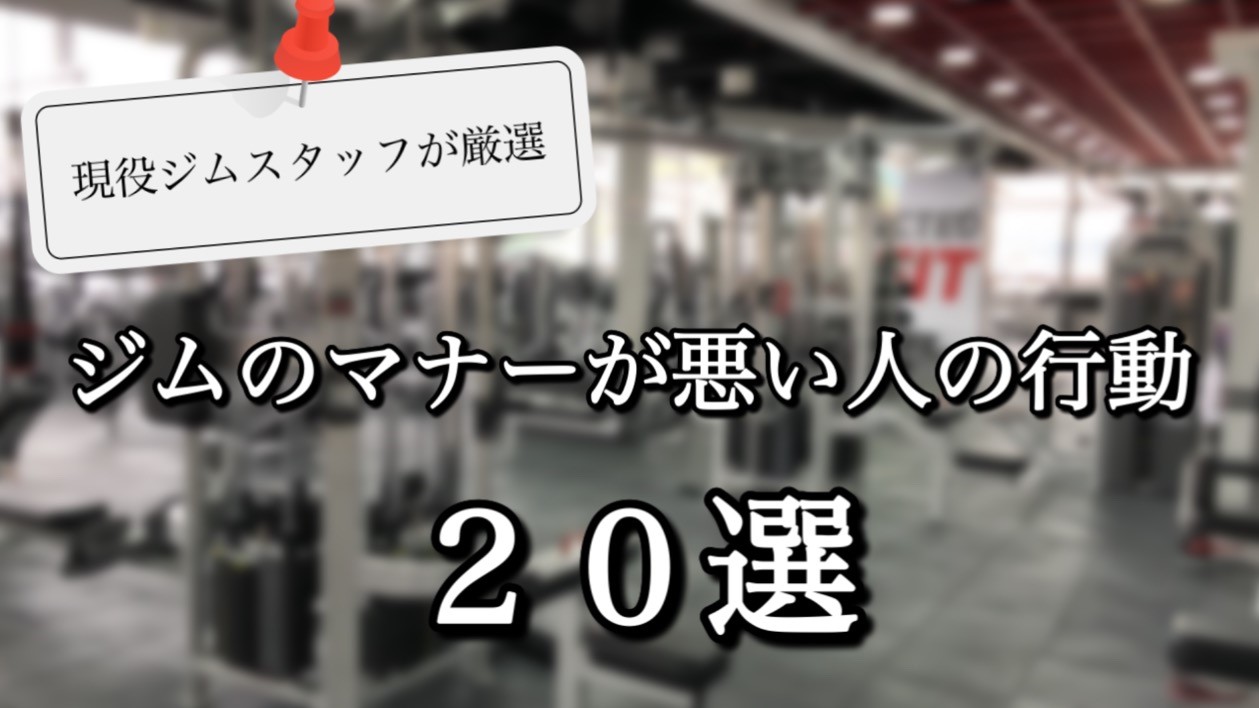
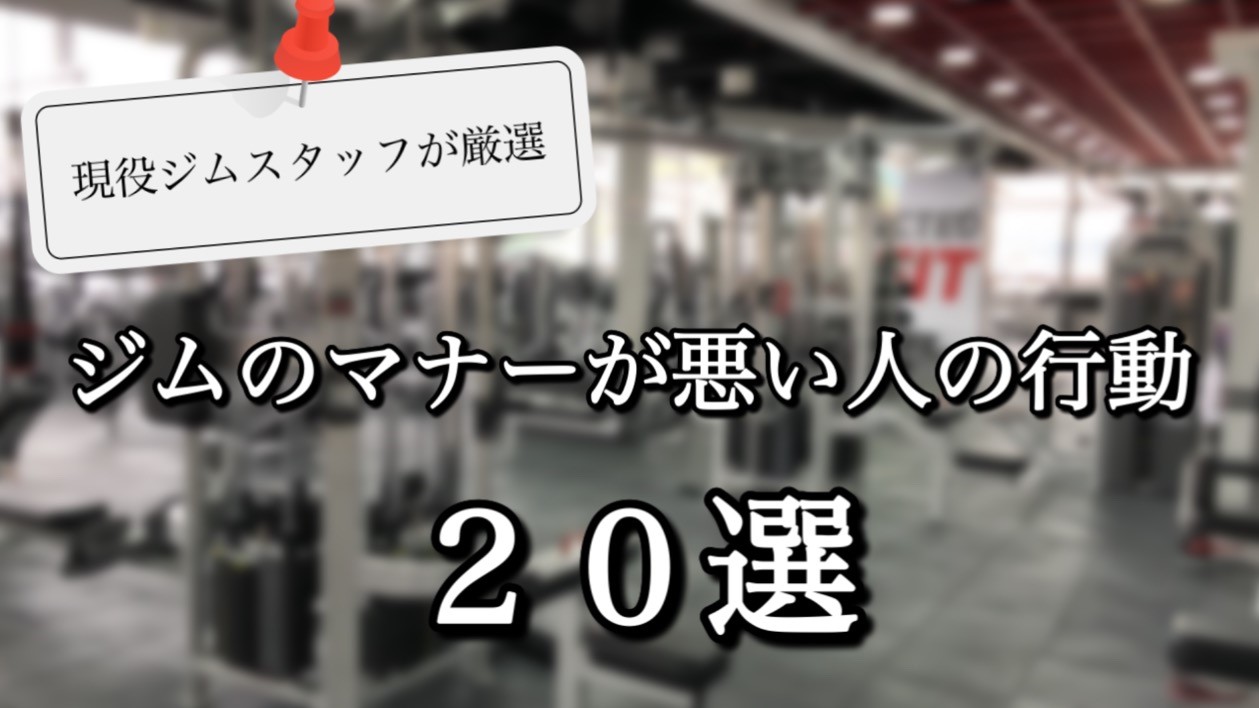
重量とレップ数を変える
種目や順番と同じく固定化してしまいがちなのが、重量とレップ数です。
レップ数…1回の動作を繰り返す回数のこと
(例)ベンチプレスを10回上げ下げした場合
筋トレ界では「10レップした」という風に表現します



ちなみにレップはRepetition(繰り返し)からきています♪
皆さんも毎回同じ重量、同じレップ数でトレーニングをしていませんか?
それで重量が伸びていっているのであれば何も問題ありませんが、停滞しているのであれば少し変化を加えてみましょう!
例えば、普段「8~10レップ」狙いの中重量でトレーニングしているのなら、もう少し重くして「4~6レップ」狙いの高重量で行なう。
逆にもっと軽くして「15~20レップ以上」出来る低重量で行なうなどです。
このように重量とレップ数を変えるだけでも筋肉は新鮮な刺激として受け取りますので、ぜひこちらもお試しください♪


ただし、1回のトレーニング中に高重量、中重量、低重量と分けるのはあまりおすすめしません。
例えば、以下のような感じです↓



このやり方は中途半端であまり効率が良くありません!
ですから、高重量の日は全て高重量、低重量の日は全て低重量という風に割り切ってトレーニングを行ないましょう!
分割の仕方を変える
分割法を取り入れている人で意外と見落としがちなのが、補助筋の疲労についてです。
筋トレの動作に使われる筋肉は、大きく分けて「主動筋」と「補助筋」の2つに分類することが出来ます。
例えば、チェストプレスの動作における主動筋は「大胸筋」ですが、それを支えるのが補助筋として働く「上腕三頭筋と三角筋(前部)」です。
同じく、シーテッドローの動作における主動筋は「広背筋」ですが、それを支えるのが補助筋として働く「上腕二頭筋と三角筋(後部)」です。
このように主動筋の動きをサポートするのが補助筋なのです。
これを踏まえた上で気を付けなければならないのが、「胸や背中のトレーニングにおいても肩や腕の筋肉が使われている」という点です。
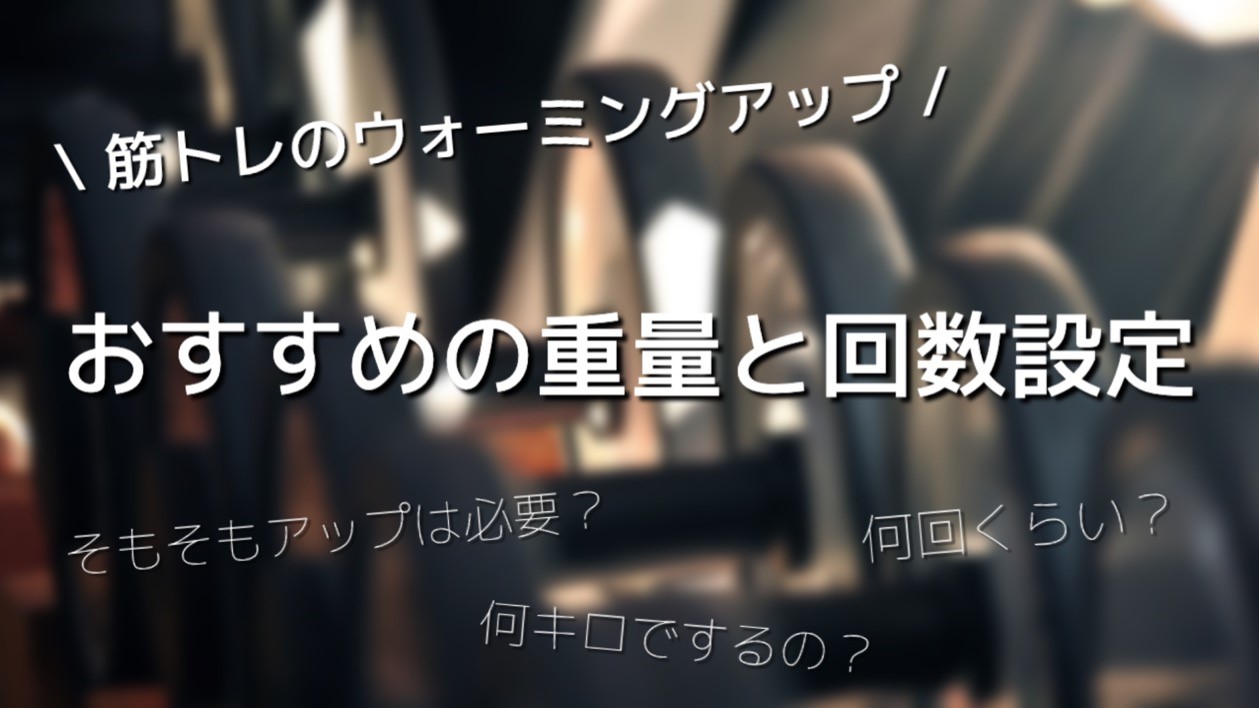
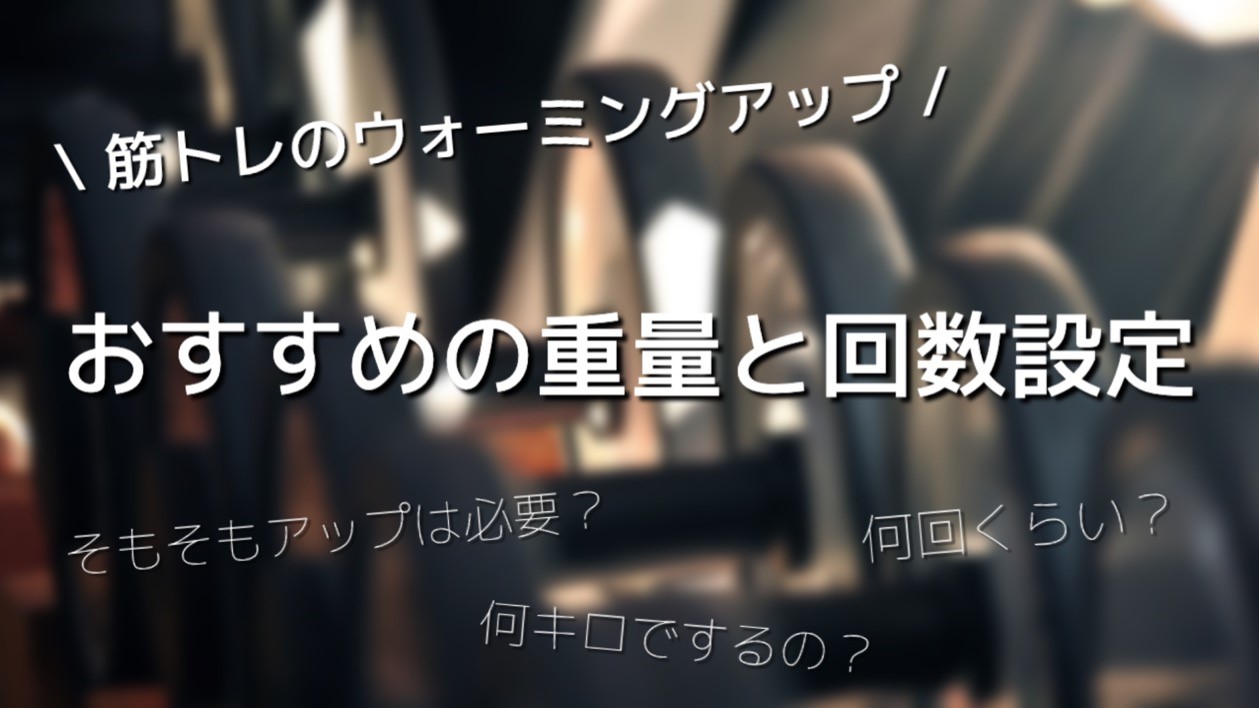
つまり、「胸と背中」を鍛えた翌日に「肩や腕」を鍛えるとなると、昨日の疲労が溜まっていて十分なパワーが発揮出来ないのです。
同じようにデッドリフトをした翌日にスクワットをするのも脊柱起立筋に疲労が溜まっていて出来たものではありません。



1回やってみて!(笑)
もしご自身の分割の仕方が補助筋を考慮したものでない場合は、改めて各部位の組み合わせを考え直した方がいいかもしれません。
一例ですが、全身を4分割で行なうのなら以下のような感じがおすすめです。



この組み合わせなら補助筋の疲労もあまり関与しません♪
トレーニング頻度を増やす
先ほど筋肉を大きくしたい場合、「各部位それぞれ週に1回だけのトレーニングでは頻度が低すぎる」とお伝えしました。



これについても詳しく見ていきましょう!
まず、筋肉というのは筋トレを始めた瞬間から “合成” と “分解” を開始します。
バーベルカールであれば、バーを持って腕を曲げた1レップ目から “合成” と “分解” が始まるのです。
初めのうちは “分解” の方が優勢ですが、だんだんと “合成” の方が上回ってきて、筋トレ直後1~3時間は合成力がピークに達します。
その後も緩やかに合成は続き、最大72~96時間程度は続くとされているのです。



つまり、筋肉は筋トレ後も3~4日は成長する!
ここで話を戻しますが、各部位をそれぞれ週に1回ということは、各部位ともトレーニングの間が6日間も空いてしまうことになります。
これでは筋肉の成長が完全に止まってから次の刺激を与えることになり、効率が悪くなってしまうのです。
そこで、おすすめなのが各部位を中4~5日のペースで鍛えることです。
このペースであれば合成力が落ち着いたところで次の刺激を与えることになるので、無駄な空白期間がなく、非常に効率的と言えます。
中4日で「胸トレ」を行なう場合
(月) → (土) → (木) → (火) → (日) …
↑ご覧のようにだんだんと曜日がズレていく形になります
もちろん、皆さんお忙しいと思いますので、ご自身の出来る範囲で試してもらえればと思います。
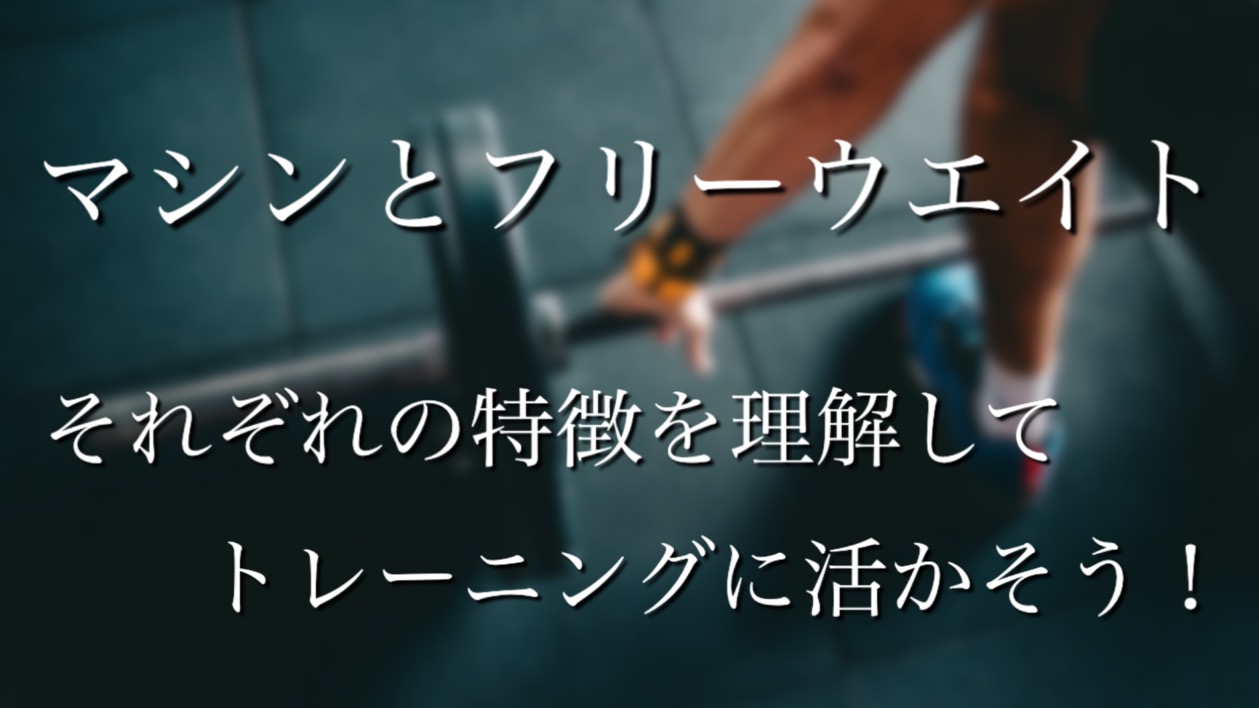
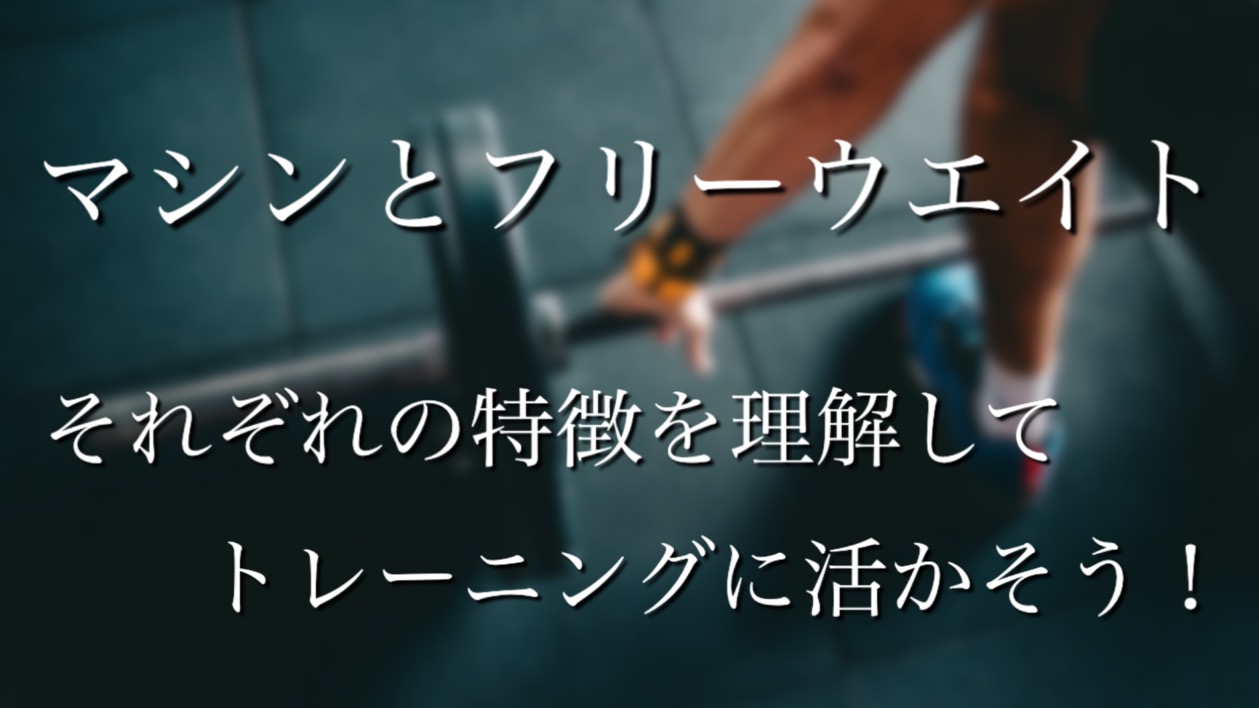
頑張りすぎない
一昔前は「気合・根性・努力」など「頑張れば頑張るほど成果が出る」みたいなことを周りの大人たちから言い聞かされました。
それゆえに僕と同じ30代以降の人には、まだまだ親や先生から言われてきた根性論が染みついているのではないでしょうか?



しかし、今は令和です!



もう少し効率的にいきましょう!
先ほど筋肉を成長させるのに必要なのは「今の限界を “ほんの少しだけ” 超える刺激」とお伝えしました。
これはつまり、今の限界が100であれば101の刺激さえあれば十分ということになります。
もちろん、それ以上の150や200といった刺激を与えても筋肉は成長しようとしますが、その分回復に時間がかかるので非効率です。



いわゆるオーバーワーク!
これはトレーニーあるあるだと思いますが、筋トレ後に何日も筋肉痛が続くと追い込めた気がしてメンタル的にも安心しますよね?
しかし、このような強すぎる刺激はストレスを感じると体内に分泌される「コルチゾール」というホルモンを増やしてしまいます。
これの何がいけないのかと言いますと、コルチゾールは筋肉の分解を促進させる作用があるからです。
これではせっかく筋肉が合成されても、すぐにまた分解されるという三歩進んで二歩下がる状態になってしまいます。



なんだか無駄な努力な気がする…
だからこそ「限界を “ほんの少しだけ” 超える刺激」がベストなのです!
\ おすすめのトレーニングギア /
限界の見分け方
では、どれくらいの刺激が「限界を “ほんの少しだけ” 超えた状態」なのでしょうか?
まず、筋トレをして翌日もしくは翌々日に筋肉痛が来れば間違いなく限界を超えていると考えてください。
しかし、先ほどもお伝えした通り、筋肉痛が何日も続くのは限界を超えすぎてしまった状態です。
大体、筋肉痛が来て翌日もしくは翌々日には痛みが消えている程度がベストですので、ご自身でそうなるようにトレーニングの内容を調節してください。



筋肉痛が何日も続く場合は種目やセット数を減らしましょう!
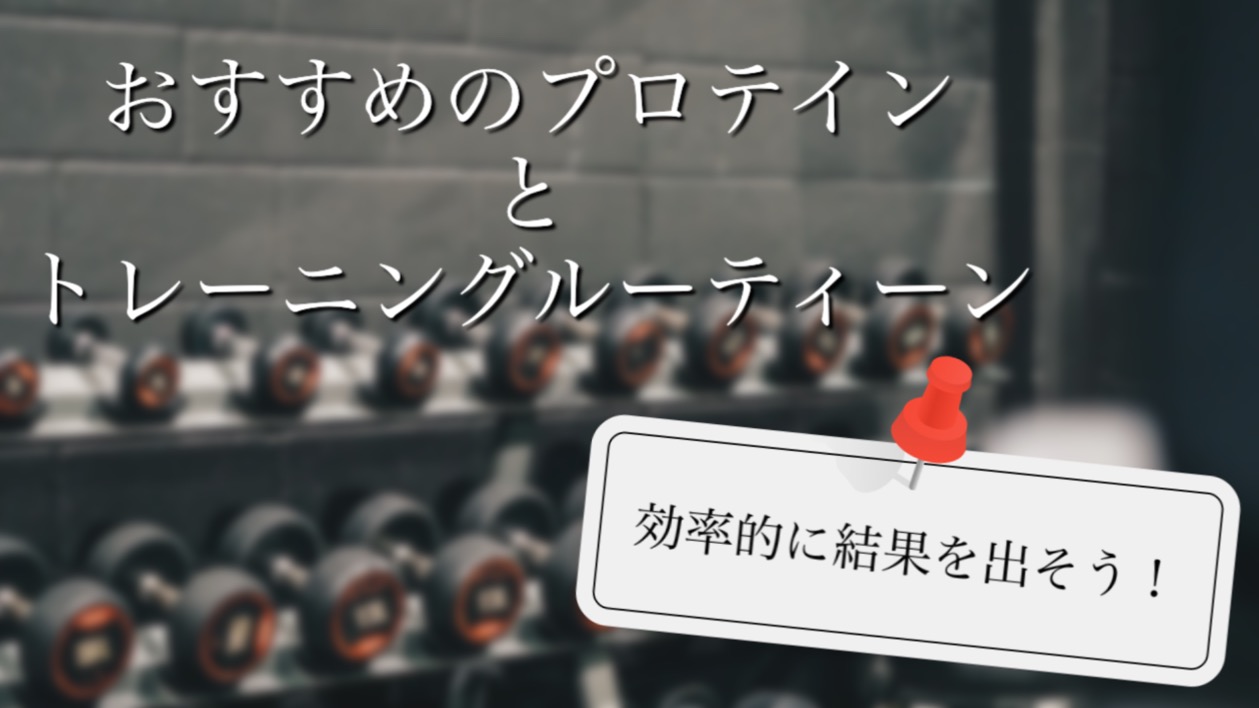
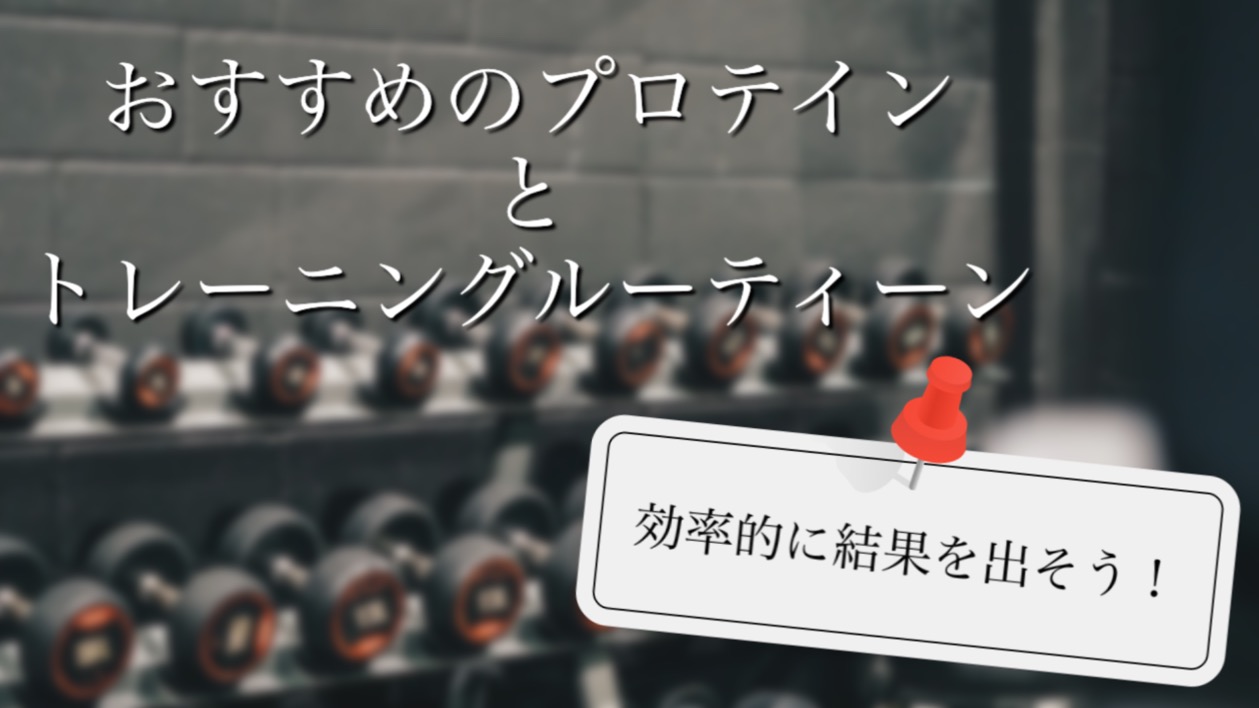
また、ポジティブフェイラー(Positive Failure)という言葉があります。
これはポジティブ動作がフェイラー(失敗)する、つまりポジティブ動作が出来なくなる状態のことを意味します。
< ポジティブフェイラーの例 >
・ベンチプレスの場合 → バーを胸に下ろした状態から上がらない
・スクワットの場合 → かかんだ状態から立ち上がれない
・チンニングの場合 → ぶら下がった状態から上がれない
このようにポジティブフェイラーまで追い込めば限界を超えていると考えていいかと思います。
仮に1セット目と2セット目は10回出来て、3セット目でポジティブフェイラーとなり7回しか出来なかったとします。
この場合、その種目は十分追い込めたので4セット目は必要ないということです。



逆に何セットでも出来るのは1セットの強度が低い証拠!
ただし、筋肉量や回復力には個人差があるので、ある人にとっては十分な刺激でも、ある人にとっては物足りないこともあります。
やはり大切なのは、筋トレ後の成長具合を見ながらご自身で自分にとっての限界ラインを見つけていくことかと思います。
まとめ
< 筋トレが停滞する人の3つの特徴 >
・毎回同じ「種目・重量・レップ数」で新鮮な刺激を与えられていない
・「頑張れば頑張るほど成果が出る」という思い込みがオーバーワークを招いている
・各部位のトレーニング頻度が低すぎる
< 筋トレが停滞したら変えるべき効果的な対策5選 >
① 種目や順番を変えて新鮮な刺激を与える
② 重量とレップ数を変えて新鮮な刺激を与える
③ 補助筋を考慮した分割法を取り入れる
④ 各部位につき中4~5日の頻度でトレーニングを行なう
⑤ 頑張り過ぎず、限界を超えるのはほんの少しだけにする
今回は筋トレが停滞する人の3つの特徴と今すぐ変えるべき効果的な対策5選をお伝えしました。
もし当てはまっている人がいたら、ぜひ今回の内容を参考に変化を加えてみてください。
皆さんがプラトーから抜け出し、さらに高みへ行けることを願っています♪



筋トレって奥が深いよね~!
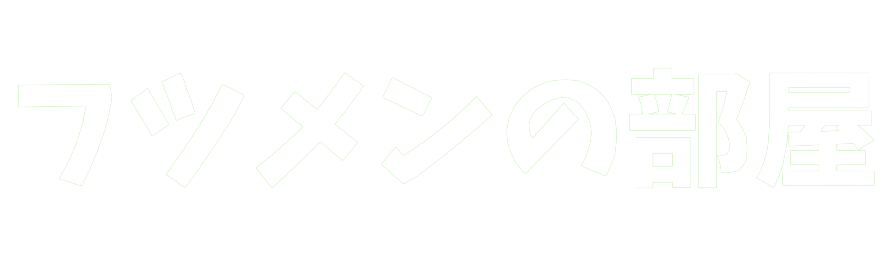
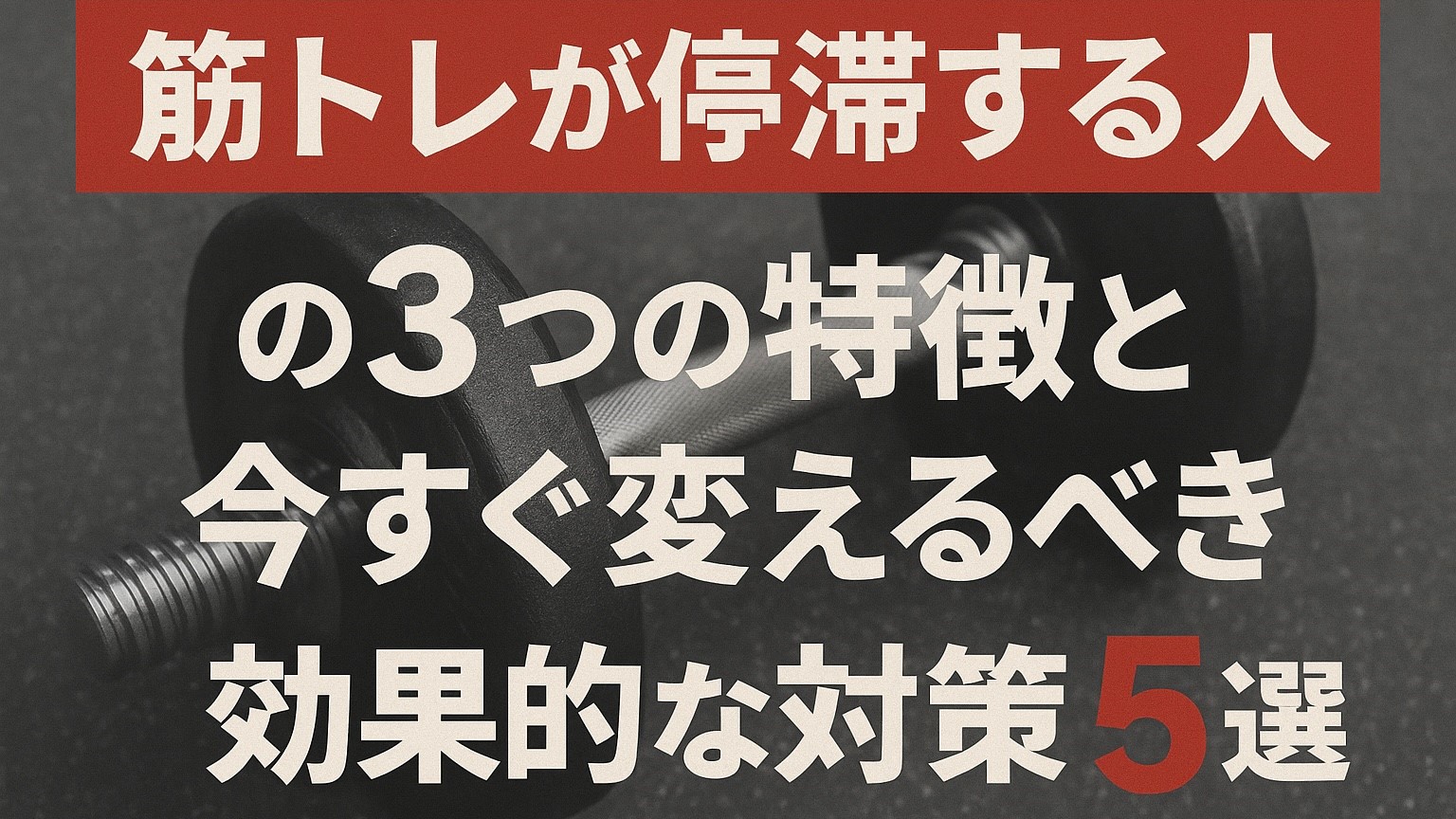
コメント